『第三次国連海洋法会議』
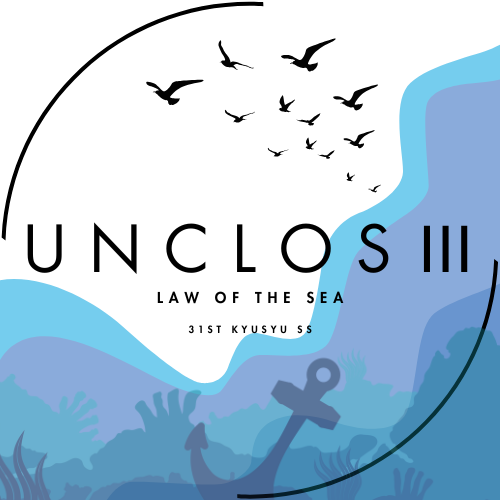
【議題概要】
国連海洋法条約は17部320条と9つの附属書から構成される条約である。海洋秩序を作る包括的・普遍的な本条約はしばしば「海の憲法」とも呼ばれる。各国の思惑が交錯するこの条約をこの夏、別府で新たに作り上げようではありませんか。
会議設定
| 議題 | 第三次国連海洋法会議 |
| 設定議場 | 第三次国連海洋法会議 注)会期は未定ですが、決定次第HPの更新などを行います。 |
| 設定日時 | 未定 |
| 使用言語 | 公式/非公式/文書=日/日/日(動詞のみ英語併記) |
| 募集人数 | 35~40人(シングル、ペアどちらも可) 注)ペアのマッチング制度を行います。ただし、人数が少ない場合は実施いたしません。 |
会議コンセプト
『Frontier』
コンセプトは「Frontier」です。模擬国連は楽しいのか?そして、何を目的として行っているのか?この問いに対する答えは人それぞれかもしれません。私は模擬国連が大好きです。そして常に楽しいと思います。リサーチ中の知らないことを知るワクワク、フロントからたくさんサポートをしてもらいたくさんのアイデアが湧く瞬間、睡眠不足になりながらもロジックを考える時、会議場への移動中の緊張と高揚、扉を開けてみんなと出会う瞬間、出席確認の応答、自国のスピーチ、モデの緊張感、アンモデの雑多として雰囲気、緊張高まる投票行動、最後のあじゃん、アフターで交わす大使同士の新たな交流。もはや模擬国連ジャンキーかもしれません。これまでの九州SSはそんなジャンキーたちがジャンキーたちと交流し、新たなジャンキーを創りあげていったことでしょう。私はそんな会議にしたいと思います。しかしながらみんながみんな全てが楽しい!最高!なんて思うドMではないしそれぞれ苦しい思いをすることもあるでしょう。全てを楽しいと思う必要はありません。ただ一つ言えるのは、せっかく夏休みの貴重な時間とお金を使って参加するからには、「楽しかった」「成長できた」と心から思えるような会議にしたいということです。
何となく会議を進めてしまえば、気づかぬうちにダラダラとした時間が流れてしまうかもしれません。だからこそ、すべての行動において「自分は何を目的としてこの行動を取っているのか」「その目的のために、どのような手段を選び、どう実行していくのか」といった意識を持つことが重要だと思います。
この会議は決して難易度の高いものではないからこそ、自分なりの工夫や発想を試すチャンスでもあります。多角的に物事を考え、たくさんの思考を重ねることで、それがやがて国益の追求につながっていくはずです。自分なりのスタイルや進め方を見つけ、あるいは新たに築いていく。そんなプロセスそのものを楽しめるような会議にしていきたいと思います。
一夏の思い出として皆さんも九州で「模擬国連ジャンキー」になりませんか。フロント・事務局一同皆様の参加を心よりお待ちしております。
会議の特徴
本会議では海の憲法とも名高い国際海洋法の一般を定めた国連海洋法条約を扱います。史実では時は遡り国際連盟期のハーグ法典化会議まで遡ります。この会議では決定的な合意を生むことはできず、戦後第一次海洋法会議にてジュネーブ4条約が採択・発効しました。しかしながら領海幅など重大な論点を残したまま、第二次海洋法会議を開催しましたがここでは何も成果を出すことができませんでした。その後、10年の時を経て再び会議が招集されました。こうした経緯を経て、1973年に第三次国連海洋法会議が招集され、実に9年にわたる交渉が開始されました。この会議は、海洋に関するあらゆる問題を包括的に取り扱うことを目的とし、過去の会議では解決しきれなかった領海幅、資源配分、環境保護、航行の自由、島の扱い、国際海峡の制度など、極めて多岐にわたるテーマを網羅しました。特に注目すべきは、以下の主要議題が三つの委員会に分けられて審議された点です。第一委員会では、深海底の鉱物資源開発に関する制度設計が議論されました。ここでは、深海底が「人類の共同の財産(common heritage of mankind)」であるという原則が提示され、その管理主体としての国際海底機構の設立構想が浮上しました。第二委員会では、領海、接続水域、排他的経済水域(EEZ)、大陸棚、群島国家制度など、国家の主権的権利に関わる制度が議論されました。ここでは、特に排他的経済水域200海里制度の創設が大きな転換点となりました。第三委員会では、海洋環境の保護と海洋汚染防止に関する原則や国家の義務が焦点となり、各国の管轄権、監督義務、責任体制などが詳細に検討されました。
特に本会議では第二委員会で話された内容と第三委員会にて話し合われた海洋汚染の国際的枠組みと管轄権について扱う予定です。(会議設計は変更の可能性があります)
このように、第三次海洋法会議は、国家間の利害が鋭く対立する中で、柔軟な交渉メカニズムとコンセンサス方式を採用し、1982年に国連海洋法条約(United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)という形で結実しました。この条約は「海の憲法」とも称され、現在に至るまで国際海洋秩序の根幹を成しています。
フロント紹介

ディレク
染谷 真樹
立命館アジア太平洋大学
サステナビリティ観光学部 3年
九州支部 老メン

議長
松永 悠希
東京外国語大学
国際社会学部 3年
国立研究会 老メン

秘書官
井田 慎一郎
金沢大学
法学類 4年
北陸支部 神メン
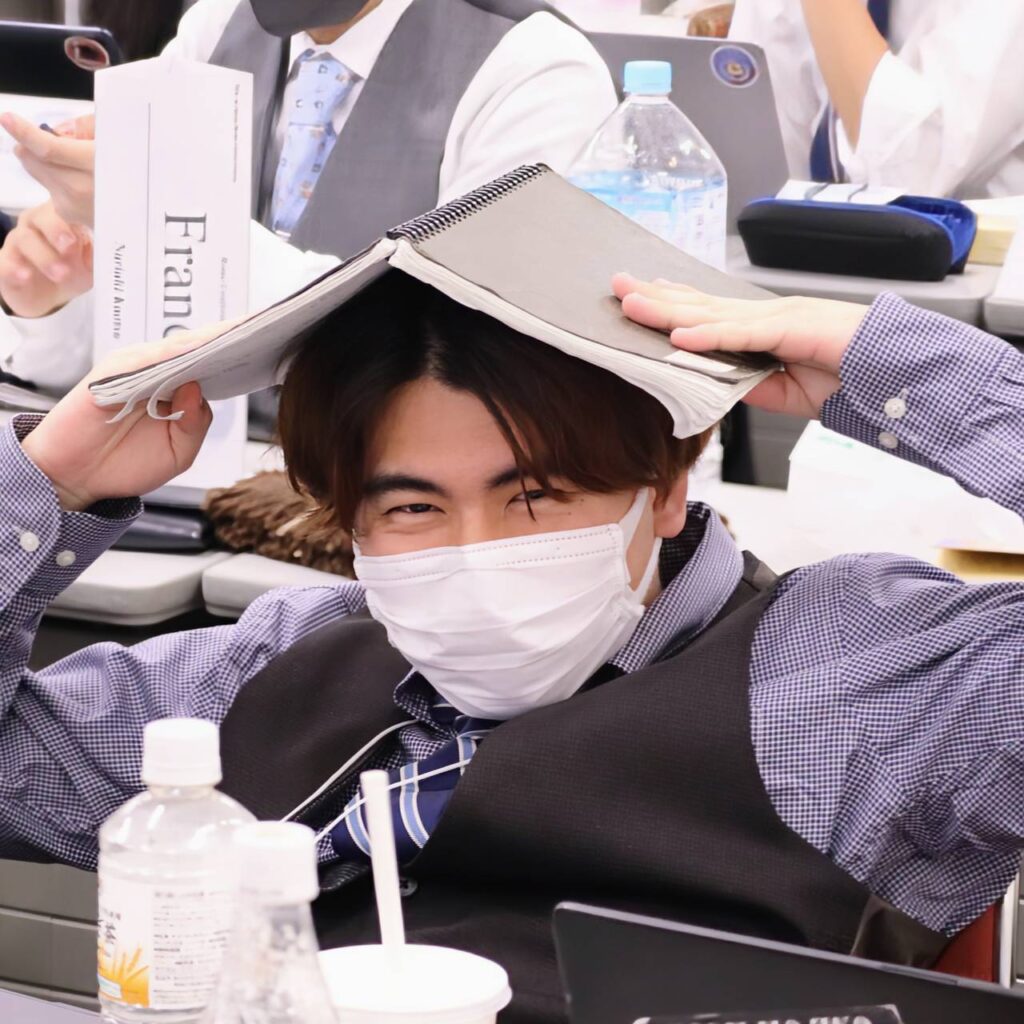
秘書官
中野 涼太
大阪大学
人間科学部 2年
神戸研究会 旧メン